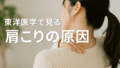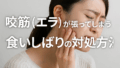はじめに
毎月訪れる生理痛に悩まされている女性は少なくありません。鎮痛剤を手放せない、仕事や学業に支障が出る、寝込んでしまうほどの痛みがある――こうした症状は決して「我慢すべきもの」ではありません。西洋医学では鎮痛剤やホルモン療法などの対症療法が中心となりますが、東洋医学では身体全体のバランスを整えることで、根本的な体質改善を目指します。
本コラムでは、東洋医学の視点から生理痛の原因を探り、日々の生活の中で実践できる養生法について詳しく解説していきます。
東洋医学から見た生理痛の原因
気血水のバランスの乱れ
東洋医学では、人体を構成する基本要素として「気・血・水」という概念があります。生理痛は、この気血水のバランスが崩れることで起こると考えられています。
気の滞り(気滞) 気は生命エネルギーであり、体内を巡って各器官の働きを支えています。ストレスや緊張によって気の流れが滞ると、子宮周辺の気の巡りも悪くなり、痛みを引き起こします。生理前にイライラしたり、胸が張ったりする症状がある方は、気滞のタイプかもしれません。
血の不足と滞り(血虚・瘀血) 血は全身に栄養を運ぶ役割を担っています。血が不足している状態(血虚)では、子宮が十分に栄養されず、生理痛が起こりやすくなります。また、血の巡りが悪く停滞している状態(瘀血)も、激しい生理痛の原因となります。瘀血がある場合、経血に塊が混じる、刺すような痛みがあるといった特徴が見られます。
冷えによる痛み(寒凝) 体内に寒邪が侵入したり、もともと体が冷えやすい体質の場合、血液の流れが悪くなり、子宮が冷えて痛みが生じます。温めると楽になる、冷たいものを摂ると悪化する場合は、冷えが原因の可能性が高いでしょう。
湿熱の停滞 体内に余分な水分や熱が溜まっている状態では、重だるい痛みや下腹部の膨満感を伴う生理痛が起こります。おりものが多い、黄色っぽいなどの症状がある場合は、湿熱タイプかもしれません。
五臓六腑との関係
東洋医学では、生理と深く関わる臓器として「肝・脾・腎」の三つが特に重要視されます。
肝の働き 肝は気の流れをコントロールし、血を貯蔵する役割があります。肝の機能が低下すると気血の流れが滞り、生理痛やPMS(月経前症候群)が起こりやすくなります。
脾の働き 脾は消化吸収を司り、気血を生成します。脾が弱ると血が不足し、生理痛の原因となります。また、脾は「統血」といって血を血管内に保持する働きもあるため、脾の機能低下は経血量の異常にもつながります。
腎の働き 腎は生命力の源である「精」を蓄え、生殖機能を支えています。腎が弱ると子宮を温める力が不足し、冷えによる生理痛が起こりやすくなります。
生理痛のタイプ別養生法
気滞タイプの養生
特徴
- 生理前から張るような痛みがある
- イライラしやすい
- 胸や脇が張る
- 経血の量や周期が不安定
養生のポイント 気の流れをスムーズにするためには、ストレス管理が最も重要です。深呼吸や軽い運動で気を巡らせましょう。柑橘類の香りはリラックス効果があり、気の巡りを助けます。
おすすめの食材 香りのよい食材が気の巡りを改善します。柑橘類(みかん、グレープフルーツ、レモン)、ジャスミン茶、ミント、セロリ、三つ葉、シソ、玉ねぎなどを積極的に取り入れましょう。
避けるべきこと 過度なストレス、睡眠不足、不規則な生活は気の流れを乱します。また、思い詰めすぎず、適度に気分転換をすることが大切です。
血虚タイプの養生
特徴
- 生理の後半や終わりかけに鈍い痛みがある
- 経血量が少ない、色が薄い
- めまい、立ちくらみがある
- 顔色が悪い、爪が割れやすい
- 疲れやすい
養生のポイント 血を補う食材を積極的に摂り、十分な睡眠を取ることが重要です。夜更かしは血を消耗するため避けましょう。特に生理後は血を補う時期として大切です。
おすすめの食材 黒い食材や赤い食材が血を補います。黒豆、黒ごま、黒きくらげ、ひじき、プルーン、なつめ、クコの実、レバー、赤身肉、ほうれん草、人参、ビーツなどがおすすめです。
避けるべきこと 過度のダイエット、激しい運動、目の使いすぎ(血を消耗します)、夜更かしは血虚を悪化させます。
瘀血タイプの養生
特徴
- 刺すような鋭い痛みがある
- 痛む場所が固定している
- 経血に塊が混じる
- 経血の色が暗い、黒っぽい
- 生理前から痛みが始まる
養生のポイント 血の巡りを改善することが最優先です。適度な運動で血流を促進し、体を温めることが大切です。長時間同じ姿勢でいることは避けましょう。
おすすめの食材 血の巡りを良くする食材として、青魚(サバ、イワシ、サンマ)、玉ねぎ、にんにく、生姜、ネギ、らっきょう、黒酢、紅花茶、ターメリックなどがあります。
避けるべきこと 冷たい食べ物や飲み物、体を冷やす環境、長時間のデスクワークや座りっぱなしの姿勢、運動不足は瘀血を悪化させます。
寒凝タイプの養生
特徴
- 下腹部が冷えて痛む
- 温めると楽になる
- 手足が冷たい
- 経血の色が暗く、塊が出ることもある
- 寒い季節に悪化する
養生のポイント とにかく体を温めることが重要です。下腹部や腰回りを冷やさないよう、腹巻きやカイロを活用しましょう。入浴も効果的です。
おすすめの食材 体を温める食材として、生姜、にんにく、ネギ、シナモン、山椒、唐辛子(適量)、羊肉、鶏肉、えび、くるみ、栗などがおすすめです。温かい飲み物や料理を選びましょう。
避けるべきこと 冷たい飲食物、生もの、薄着、冷房の効きすぎた環境、冷たいものでの足浴やシャワーだけの入浴は避けましょう。
湿熱タイプの養生
特徴
- 重だるい痛みがある
- 下腹部の膨満感
- おりものが多い、黄色っぽい
- 口が粘る、口臭がある
- 経血が粘っこい
養生のポイント 余分な湿と熱を取り除くことが目標です。油っこいものや甘いものを控え、消化に良い食事を心がけましょう。適度な運動で発汗を促すことも効果的です。
おすすめの食材 湿を取り除く食材として、はと麦、小豆、冬瓜、きゅうり、セロリ、緑茶、はぶ茶などがあります。また、熱を冷ます食材として、ゴーヤ、れんこん、大根などもおすすめです。
避けるべきこと 脂っこい食事、甘いもの、乳製品の過剰摂取、アルコール、味の濃いもの、食べ過ぎは湿熱を悪化させます。
日常生活での養生法
食事の養生
基本的な食事の考え方 東洋医学では「医食同源」という言葉があるように、日々の食事が健康の基盤となります。生理痛改善のためには、以下の点を意識しましょう。
- 規則正しい食事時間を守る
- 腹八分目を心がける
- よく噛んで食べる
- 旬の食材を取り入れる
- 極端に偏った食事を避ける
生理周期に合わせた食事 生理後(卵胞期)は血を補う時期です。鉄分やタンパク質を豊富に含む食材を積極的に摂りましょう。排卵期は気血のバランスを整える時期です。バランスの良い食事を心がけます。生理前(黄体期)は気の巡りを良くする食材と、むくみを予防する食材を取り入れます。生理中は体を温める食材と消化の良いものを選びましょう。
避けたい食習慣 冷たい飲み物の過剰摂取、空腹時の甘いものの摂取、夜遅い時間の食事、早食い、ながら食いなどは、脾胃の働きを弱め、気血の生成を妨げます。
運動と休息
適度な運動の重要性 運動は気血の巡りを良くし、ストレス解消にもなります。ただし、過度な運動は気血を消耗するため、適度な強度が大切です。
おすすめの運動 ウォーキング、ヨガ、太極拳、気功、ストレッチなど、ゆったりとした動きで体を温め、気血を巡らせる運動が適しています。特に骨盤周りの血流を改善する骨盤体操やヨガのポーズは効果的です。
運動のタイミング 生理中の激しい運動は避け、軽いストレッチ程度にとどめましょう。生理後から排卵期は、やや積極的に運動しても良い時期です。
休息の質 十分な睡眠は気血を養います。特に夜10時から深夜2時は、肝と腎が活発に働く時間帯で、この時間に熟睡していることが理想的です。生理前後は特に無理をせず、体を休めることを優先しましょう。
温活の実践
入浴 38〜40度のぬるめのお湯に15〜20分程度ゆっくり浸かることで、全身の血流が改善されます。生理中でも、湯船に浸かることは問題ありません。むしろ体を温めることで痛みが和らぐことが多いです。
足湯 忙しくて入浴時間が取れない日でも、足湯だけでも効果があります。足は「第二の心臓」と呼ばれ、ここを温めることで全身の血流が改善されます。
カイロや腹巻き 下腹部や腰、仙骨付近を温めることで、子宮周辺の血流が良くなります。使い捨てカイロを直接肌に当てないよう注意し、服の上から使用しましょう。
温かい飲み物 常温以上の飲み物を選び、体を内側から温めます。白湯、生姜湯、ほうじ茶、紅茶などがおすすめです。
ストレス管理と心の養生
感情と生理痛の関係 東洋医学では、感情と臓腑は深く結びついていると考えられています。特に肝は感情の影響を受けやすく、怒りやイライラ、ストレスは肝の気の流れを滞らせ、生理痛を悪化させます。
リラックス法 深呼吸、瞑想、アロマテラピー、音楽鑑賞、趣味の時間など、自分なりのリラックス方法を見つけることが大切です。特に腹式呼吸は、気の巡りを整える効果があります。
人間関係の調整 無理な人間関係や、感情を抑え込む環境は気の滞りを招きます。適度な距離感を保ち、自分の感情を大切にすることも養生の一つです。
ツボ押しセルフケア
三陰交(さんいんこう) 内くるぶしの最も高い部分から、指4本分上がったところにあるツボです。婦人科系の万能ツボとも呼ばれ、生理痛、冷え、むくみなどに効果があります。両手の親指で、やや強めに3〜5秒押して離すを5〜10回繰り返します。
血海(けっかい) 膝のお皿の内側上端から、指3本分上がったところにあります。血の巡りを良くし、生理痛を和らげる効果があります。親指で円を描くようにマッサージします。
関元(かんげん) おへそから指4本分下がったところにあります。下腹部を温め、気を補う効果があります。手のひら全体で時計回りに優しくマッサージするか、カイロで温めるのも効果的です。
太衝(たいしょう) 足の親指と人差し指の骨が交わる手前のくぼみにあります。肝の気の流れを整え、イライラや気の滞りによる痛みに効果があります。
押し方のポイント 「痛気持ちいい」程度の強さで、呼吸に合わせてゆっくり押すことが大切です。強く押しすぎると逆効果になることもあるので注意しましょう。
漢方薬について
よく使われる漢方薬
生理痛に対しては、体質や症状に合わせて様々な漢方薬が用いられます。
当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん) 血虚と水滞がある、色白で冷え性の方に。むくみやすく、めまいや貧血傾向がある場合に適しています。
桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん) 瘀血タイプの方に。のぼせがあり、下腹部に圧痛があり、経血に塊が混じる場合に用いられます。
加味逍遙散(かみしょうようさん) 気滞と血虚があり、イライラしやすく、肩こりや不眠を伴う場合に。PMS症状が強い方にも適しています。
温経湯(うんけいとう) 冷えが強く、手足がほてる、唇が乾燥するなどの症状がある方に。
芎帰調血飲第一加減(きゅうきちょうけついんだいいちかげん) 産後の生理痛や、血の巡りが悪く体力が低下している方に。
漢方薬を選ぶときの注意点
漢方薬は「証」という体質や症状のパターンに合わせて選ぶことが重要です。同じ生理痛でも、人によって適する漢方薬は異なります。自己判断で選ぶのではなく、漢方に詳しい医師や薬剤師に相談し、自分に合ったものを選びましょう。
また、漢方薬は西洋薬と比べて効果が現れるまでに時間がかかることがあります。少なくとも2〜3ヶ月は継続して服用し、体質の変化を観察することが大切です。
生活習慣の見直し
睡眠の質を高める
質の良い睡眠は、気血を養い、ホルモンバランスを整える基本です。就寝前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、部屋を暗くして静かな環境を整えましょう。規則正しい就寝時間を守ることも重要です。
衣服の選び方
体を締め付ける下着や衣服は、気血の巡りを妨げます。特に生理中は、ゆったりとした服装を選びましょう。また、季節に関わらず、下半身を冷やさない服装を心がけることが大切です。
環境調整
冷房や暖房で室温を極端にしすぎず、自然な温度変化に体を慣らすことも養生の一つです。ただし、冷えは禁物なので、冷房が効きすぎている場所では、カーディガンやストールで調整しましょう。
デジタルデトックス
長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用は、目を疲れさせ、血を消耗します。また、睡眠の質を低下させ、ストレスを増やす原因にもなります。意識的にデジタル機器から離れる時間を作りましょう。
おわりに
生理痛は「我慢すべきもの」「仕方がないもの」ではありません。東洋医学の視点から自分の体質を理解し、日々の養生を実践することで、生理痛は改善できる可能性があります。
大切なのは、一度に全てを完璧にしようとするのではなく、できることから少しずつ取り入れていくことです。食事、運動、睡眠、ストレス管理など、自分の生活の中で改善できる点から始めてみましょう。
また、東洋医学の養生法は、西洋医学の治療と対立するものではありません。ひどい生理痛がある場合は、まず婦人科を受診し、子宮内膜症や子宮筋腫などの器質的な疾患がないかを確認することが重要です。その上で、西洋医学的治療と東洋医学的養生を組み合わせることで、より良い結果が得られることも多くあります。
自分の体と向き合い、体からのサインに耳を傾けること。それが東洋医学の養生の基本です。毎月の生理を「憂鬱なもの」ではなく、「自分の体を知るバロメーター」として捉え、より健やかな日々を過ごしていきましょう。
痛みが改善し、生理が快適に過ごせる日が来ることを願っています。そして、その変化は決して奇跡ではなく、あなた自身の日々の養生が積み重なった結果なのです。