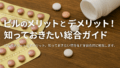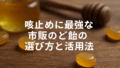はじめに
秋の訪れとともに、喉や鼻の不調を訴える人が増えてきます。朝晩の冷え込み、空気の乾燥、そして夏の疲れが残る身体。これらが重なり合って、喉のイガイガや鼻の乾燥、粘膜の不快感を引き起こすのです。現代医学では症状に応じた対症療法が中心となりますが、東洋医学の知恵である「食養生」の視点から見ると、秋特有の身体の変化に合わせた食事の工夫で、これらの不調を予防し、改善することができます。
本コラムでは、古くから伝わる食養生の知恵と現代の栄養学の知見を組み合わせながら、秋に辛くなる喉と鼻をケアする方法をご紹介します。
秋の身体はなぜ喉と鼻が辛くなるのか
東洋医学から見た秋の特徴
東洋医学では、秋は「肺」の季節とされています。肺は呼吸器系全般を司り、鼻や喉、気管支、そして皮膚までも含む広い概念です。秋になると、この肺の機能が影響を受けやすくなり、様々な不調が現れやすくなります。
秋の気候の特徴は「燥」、つまり乾燥です。この乾燥した空気が肺を傷つけ、潤いを奪っていきます。東洋医学では「燥邪(そうじゃ)」と呼ばれ、身体の津液(しんえき)という潤いを消耗させる外的要因とされています。津液が不足すると、喉や鼻の粘膜が乾燥し、バリア機能が低下してしまいます。
現代医学の視点から
現代医学的に見ても、秋の喉と鼻のトラブルには明確な理由があります。気温が下がると空気中の水分量が減少し、相対湿度が低下します。湿度が50%を下回ると、鼻や喉の粘膜が乾燥しやすくなり、ウイルスや細菌に対する防御力が弱まります。
また、夏の間に冷たい飲食物を多く摂取したり、冷房で身体を冷やしたりすることで、消化機能が低下している人も少なくありません。消化吸収力が弱まると、粘膜を健康に保つための栄養素が不足し、喉や鼻のトラブルにつながります。
食養生の基本的な考え方
潤いを補う「滋陰潤肺」
秋の食養生で最も重要なキーワードが「滋陰潤肺(じいんじゅんぱい)」です。これは、身体に潤いを与え、肺を潤すという意味です。乾燥によって失われた津液を食べ物から補い、呼吸器の粘膜を保護することが、秋の健康維持の基本となります。
滋陰潤肺の食材には、白色の食材が多いのが特徴です。東洋医学では、白い食材は肺を養うとされ、大根、れんこん、白きくらげ、梨、百合根、山芋などが代表的です。これらの食材は、実際に水分を多く含み、粘液質の成分を持つものが多く、粘膜を保護する働きがあります。
温める力と冷やす力のバランス
食養生では、食材の持つ性質を「温・熱・平・涼・寒」の五つに分類します。秋は温度差が大きく、日中は暑くても朝晩は冷え込みます。このため、極端に身体を冷やす食材や温める食材ではなく、穏やかな性質の「平性」や、適度に潤いを与える「涼性」の食材を中心に選ぶことが大切です。
ただし、すでに冷えを感じている人や、夏の冷房で身体が冷えきっている人は、温性の食材を加えてバランスを取ることも必要です。個々の体質や状態に合わせて調整することが、食養生の奥深さであり、効果を高めるポイントでもあります。
喉と鼻をケアする食材選び
白い食材の力
大根 大根は秋冬の代表的な養生食材です。辛味成分であるイソチオシアネートには抗菌作用があり、喉の炎症を和らげます。また、消化酵素であるジアスターゼが豊富で、夏に疲れた消化器を回復させる働きもあります。生で食べると辛味と酵素の効果が得られ、加熱すると優しく身体を温めます。大根おろしに蜂蜜を加えたものは、古くから咳止めとして用いられてきました。
れんこん れんこんのネバネバ成分であるムチンは、粘膜を保護し、修復する働きがあります。タンニンには止血作用と抗炎症作用があり、鼻血や喉の炎症に効果的です。ビタミンCも豊富で、加熱しても失われにくいという特徴があります。薄切りにして煮物やきんぴらにしたり、すりおろしてスープにしたりと、様々な調理法で楽しめます。
梨 梨は水分が約88%を占め、天然の潤い補給源です。東洋医学では「潤肺止咳」の効果があるとされ、乾燥による咳や痰に優れた効果を発揮します。カリウムも豊富で、むくみの解消にも役立ちます。そのまま食べるのはもちろん、蜂蜜と一緒に煮てシロップにすると、喉の薬として保存もできます。
白きくらげ 中華料理でデザートとして供される白きくらげは、究極の滋陰食材です。多糖体を豊富に含み、免疫力を高める効果があります。水で戻してから、氷砂糖や蓮の実と一緒にとろとろになるまで煮込んだ「銀耳湯(ぎんじとう)」は、秋の養生デザートとして理想的です。
種子類の滋養
松の実 良質な脂質とビタミンEが豊富な松の実は、肺を潤し、空咳を止める効果があります。そのまま食べても美味しいですが、お粥に入れたり、サラダに散らしたりすると、香ばしさと栄養をプラスできます。
くるみ オメガ3脂肪酸が豊富なくるみは、抗炎症作用に優れています。東洋医学では「補腎納気」といって、呼吸を深くし、咳を鎮める働きがあるとされています。一日3~5粒程度を目安に、そのまま食べるか、料理に加えましょう。
ぎんなん ぎんなんは肺の機能を強化し、痰を切る効果があります。ただし、食べ過ぎると中毒を起こすことがあるため、大人でも一日10粒程度までにしましょう。殻を割って炒ったものを、茶碗蒸しや炊き込みご飯に加えると、秋らしい味わいが楽しめます。
根菜類の力
山芋・長芋 ヌルヌル成分のムチンが粘膜を保護します。また、消化酵素のジアスターゼやアミラーゼが豊富で、弱った胃腸を助けます。生で食べるとこれらの酵素が活きますが、加熱すると身体を温める効果が高まります。とろろご飯、お好み焼き、グラタンなど、調理法は多様です。
里芋 食物繊維とカリウムが豊富で、腸内環境を整えながら余分な水分を排出します。独特のぬめりが胃腸の粘膜を保護し、消化を助けます。煮物や豚汁に入れると、ほっこりとした秋の味わいになります。
喉と鼻に効く薬膳的調理法
養生スープの作り方
秋におすすめなのが、潤い補給のための養生スープです。以下のレシピは、家庭で簡単に作れて、継続しやすいものです。
大根と梨の蜂蜜スープ 大根200gと梨1個を1cm角に切り、水600mlで柔らかくなるまで煮ます。火を止めて少し冷めたら、蜂蜜大さじ2を加えて完成です。喉の痛みや乾燥した咳に効果的で、優しい甘みが身体を癒します。
白きくらげと百合根の薬膳スープ 乾燥白きくらげ10gを水で戻し、百合根1個、クコの実10g、氷砂糖適量と一緒に、弱火で1時間ほど煮込みます。とろみが出てきたら完成です。就寝前に温かいうちに飲むと、翌朝の喉の調子が違います。
れんこんと鶏肉のとろとろスープ れんこん150gをすりおろし、鶏ひき肉100g、生姜のみじん切り、水600mlを鍋に入れて煮ます。塩で味を調え、最後に片栗粉でとろみをつけます。身体を温めながら粘膜を保護する、万能スープです。
お粥で胃腸から立て直す
秋は「粥養生」の季節でもあります。お粥は消化吸収が良く、胃腸に負担をかけずに栄養を補給できます。また、水分量が多いため、身体に潤いを与えます。
基本の薬膳粥 米1合に対して水6~7倍の水で炊きます。炊き上がりの30分前に、大根の薄切り、れんこんの薄切り、松の実、クコの実などを加えます。塩で薄く味付けし、仕上げに胡麻油を数滴たらします。朝食にこのお粥を食べることで、一日の始まりに身体を優しく目覚めさせることができます。
飲み物の工夫
蜂蜜大根 大根を1cm角に切り、蜂蜜に漬けて一晩置きます。翌朝には大根から水分が出て、シロップができます。このシロップを大さじ1杯、お湯で割って飲むと、喉の痛みや咳に即効性があります。
生姜蜂蜜レモン 生姜の薄切りとレモンスライスを蜂蜜に漬けておきます。お湯を注いで飲むと、身体が温まり、喉も潤います。殺菌作用もあるため、風邪の予防にもなります。
なつめ茶 乾燥なつめ5~6個を軽く割って、熱湯を注ぎ10分ほど蒸らします。なつめは「補気養血」といって、気力と血を補う食材です。疲れやすい人や、貧血気味の人に特におすすめです。
避けたい食べ物と食べ方
乾燥を悪化させる食材
秋の食養生では、以下のような食材や食べ方は控えめにすることが望ましいです。
辛すぎる香辛料 唐辛子、山椒、胡椒などの刺激の強い香辛料は、身体を温める効果はありますが、津液を消耗させ、さらなる乾燥を招きます。完全に避ける必要はありませんが、量を控えめにしましょう。
揚げ物や炒め物 油で高温調理した食べ物は、「燥熱」を生み出し、喉や鼻の粘膜を刺激します。特に、カリカリに揚げたスナック菓子やポテトチップスなどは、直接喉を傷つける原因にもなります。
冷たすぎる飲食物 秋は身体を冷やしすぎないことも重要です。冷たいビールやアイスクリーム、かき氷などは、胃腸の働きを弱め、結果的に粘膜を健康に保つ力を低下させます。
甘すぎるもの 白砂糖を大量に使った甘いお菓子は、「痰湿」といって、粘りのある痰を生み出す原因になります。喉や鼻の不快感がある時は特に控えましょう。
食べ方の注意点
よく噛むこと 唾液には粘膜を保護する成分が含まれています。よく噛むことで唾液の分泌が促され、口腔から喉にかけての潤いが保たれます。一口30回を目標に、ゆっくり食事を楽しみましょう。
温かいものを中心に 秋は温かい料理を中心にすることで、身体の内側から温まり、循環が良くなります。ただし、熱すぎる食べ物は粘膜を傷つけるので、適度な温度(人肌より少し温かい程度)が理想です。
腹八分目を守る 食べ過ぎは胃腸に負担をかけ、消化吸収力を低下させます。適度な空腹感を残すくらいが、東洋医学では理想とされています。
生活習慣との組み合わせ
呼吸法で肺を強化
食養生と合わせて、呼吸法を取り入れると効果が倍増します。深くゆっくりとした腹式呼吸を一日10分程度行うことで、肺の機能が高まり、粘膜の血流も改善されます。
朝、窓を開けて新鮮な空気を吸い込みながら、鼻から4秒かけて吸い、8秒かけて口からゆっくり吐く。これを10回繰り返すだけで、一日の呼吸が楽になります。
適度な湿度管理
食事で内側から潤いを補給すると同時に、外側からも乾燥を防ぎましょう。室内の湿度は50~60%が理想です。加湿器を使用するか、濡れタオルを干す、観葉植物を置くなどの工夫で、快適な湿度を保ちます。
特に就寝時の乾燥は喉に大きなダメージを与えるため、寝室の湿度管理は重要です。マスクをして寝るのも、簡単で効果的な方法です。
適度な運動
軽い運動は血液循環を促進し、全身の代謝を高めます。特に、ウォーキングや太極拳のようなゆったりとした運動は、肺の機能を高めるのに適しています。秋の爽やかな空気の中での散歩は、気分転換にもなり、ストレス軽減にもつながります。
睡眠の質を高める
東洋医学では「肺は憂いを司る」といわれ、心の状態が肺の健康に影響します。十分な睡眠は心身の回復に不可欠です。就寝の2時間前には食事を終え、1時間前には照明を落として、リラックスする時間を持ちましょう。
温かい白きくらげのスープを寝る前に飲むことで、身体が温まり、潤いも補給され、質の良い睡眠につながります。
体質別のアレンジ
冷え性の人
基本の滋陰食材に、温性の食材を組み合わせます。生姜、シナモン、黒砂糖、羊肉、鶏肉などを加えることで、潤いを補給しながら身体を温めることができます。大根や梨は加熱して食べることで、冷やす性質を和らげられます。
熱がこもりやすい人
顔が赤い、口が渇く、便秘がちという人は、身体に熱がこもっている可能性があります。このタイプは、梨やきゅうり、トマト、豆腐など、涼性の食材を積極的に取り入れます。ただし、冷やしすぎないよう、常温か軽く温めて食べるのがコツです。
疲れやすい人
気力が不足している人は、栄養をしっかり補給することが先決です。鶏肉、卵、山芋、きのこ類、黒ごまなど、「補気」や「補血」の食材を基本の滋陰食材と組み合わせます。消化の良い形で調理し、少量ずつでも継続して食べることが大切です。
まとめ:秋の養生は冬への準備
秋の食養生は、単に喉や鼻の症状を和らげるだけでなく、来たる冬に向けて身体の基礎を作る大切な時期でもあります。潤いを補い、肺の機能を高めることで、冬の風邪やインフルエンザにも負けない身体作りができます。
食養生の素晴らしいところは、特別な材料や難しい調理法が必要ないことです。季節の食材を丁寧に選び、身体の声に耳を傾けながら、日々の食事を整えていく。その積み重ねが、健康な身体を作り上げていきます。
喉がイガイガする、鼻が乾燥する、そんな小さな不調を見逃さず、食事から見直してみてください。白い食材を意識して選ぶ、温かいスープを一日一杯飲む、よく噛んで食べる。こうした小さな習慣が、秋を快適に過ごす秘訣となります。
古の人々が経験と観察から編み出した食養生の知恵は、現代を生きる私たちにとっても、大きな指針となります。自然のリズムに寄り添い、季節の恵みをいただきながら、喉と鼻、そして全身の健康を守っていきましょう。秋の食卓が、あなたの健康を支える薬膳の場となりますように。