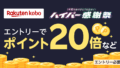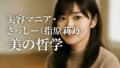はじめに
疲れた時、ストレスを感じた時、あるいは特に理由もなく無性に甘いものが食べたくなる――そんな経験は誰にでもあるでしょう。現代の栄養学では、これを血糖値の変動やセロトニンなどの神経伝達物質の影響として説明しますが、東洋医学では数千年の歴史の中で、より深い視点から「甘味への渇望」を捉えてきました。
本コラムでは、東洋医学の観点から甘いものが食べたくなる理由を紐解き、その根本的な対策について詳しく解説していきます。
東洋医学における「甘味」の位置づけ
五味と五臓の関係
東洋医学では、食べ物の味を「酸・苦・甘・辛・鹹(かん)」の五つに分類します。これを「五味」と呼び、それぞれが特定の臓腑(内臓)と深い関係を持っています。
- 酸味:肝・胆
- 苦味:心・小腸
- 甘味:脾・胃
- 辛味:肺・大腸
- 鹹味(塩辛い味):腎・膀胱
この中で甘味は「脾(ひ)」と「胃」に対応しています。東洋医学における「脾」は、西洋医学の脾臓とは異なり、消化吸収全般を司る広い概念です。現代の言葉で言えば、胃腸の消化機能、膵臓の機能、さらには栄養の運搬・代謝にも関わる重要な臓器と考えられています。
甘味の本来の役割
東洋医学では、甘味には「補益(ほえき)」つまり身体を補い養う作用があるとされています。適度な甘味は:
- 気(エネルギー)を補う:生命活動の源となるエネルギーを生み出す
- 脾胃の働きを助ける:消化吸収機能を正常に保つ
- 緊張を緩める:筋肉や精神の緊張をほぐす
- 調和を促す:他の味との調和を取り、薬の作用を和らげる
つまり、甘味は本来、身体にとって必要不可欠なものなのです。問題は、その「質」と「量」にあります。
甘いものが食べたくなる東洋医学的理由
1. 脾気虚(ひききょ)
最も一般的な原因が「脾気虚」です。これは、脾の気(エネルギー)が不足している状態を指します。
症状の特徴:
- 疲れやすい、倦怠感
- 食後の眠気や身体の重だるさ
- 軟便または下痢傾向
- 食欲不振と過食の繰り返し
- 考え事をするとすぐに疲れる
- 甘いものを食べても満足感が続かない
脾気虚の状態では、本来なら食べ物から気を生み出す力が弱まっています。身体は手っ取り早くエネルギーを得ようとして、即座に吸収される甘味を欲するのです。しかし、白砂糖のような精製された甘味は一時的なエネルギー源にはなっても、脾の負担を増やすだけで根本的な解決にはなりません。
原因:
- 不規則な食事
- 過度の思い悩み(思慮過度)
- 慢性的な疲労
- 冷たいものの摂り過ぎ
- 生ものや消化の悪いものの過食
2. 脾陽虚(ひようきょ)
脾気虚がさらに進行すると「脾陽虚」になります。これは気の不足に加えて、身体を温める陽気も不足している状態です。
症状の特徴:
- 手足の冷え、特に腹部の冷え
- 水様性の下痢
- むくみやすい
- 温かいものや甘いものを欲する
- 舌が腫れぼったく、白い苔がつく
脾陽虚の人は、身体が常に冷えているため、温かさを求めると同時に、即座にエネルギーに変わる甘味を強く欲します。チョコレートやケーキなど、糖分と脂肪を含む高カロリーのものを特に求める傾向があります。
3. 肝鬱気滞(かんうつきたい)
現代人に非常に多い状態が「肝鬱気滞」です。これは、ストレスや感情の抑圧によって、肝の気の流れが滞っている状態を指します。
症状の特徴:
- イライラしやすい、怒りっぽい
- ストレスを感じると甘いものが欲しくなる
- 胸や脇腹が張る感じ
- ため息が多い
- 月経前症候群(PMS)が強い(女性の場合)
- 情緒不安定
東洋医学では「肝木克脾土(かんもくこくひど)」という相克関係があります。肝の気が滞ると、その影響が脾胃に及び、消化機能が乱れます。すると脾は適切にエネルギーを生み出せなくなり、身体は甘味を求めるのです。
また、肝鬱状態では気の流れが悪いため、気持ちも詰まった感じになります。甘味には「緩める」作用があるため、無意識に甘いものを食べて気分を緩和しようとします。これが「ストレス食い」のメカニズムです。
4. 心脾両虚(しんぴりょうきょ)
過度の精神活動や心配事によって、心と脾の両方が弱っている状態です。
症状の特徴:
- 不安感、心配性
- 不眠、特に寝つきが悪い
- 動悸
- 食欲不振と甘味への渇望
- 顔色が悪い、唇が白っぽい
- 物忘れしやすい
東洋医学では「心は神を蔵す」とされ、精神活動を司ります。また「脾は思を主る」とされ、考えることと深く関わっています。現代のように情報過多で常に頭を使う生活は、心と脾の両方を消耗させます。
特にデスクワークが多く、長時間考え事をする人は、この状態になりやすいでしょう。脳は大量のエネルギーを消費するため、甘味を求めることで素早くエネルギー補給しようとします。
5. 腎陽虚(じんようきょ)
腎の陽気が不足している状態です。腎は生命エネルギーの根源を蔵する臓器とされています。
症状の特徴:
- 全身の冷え、特に腰や下半身の冷え
- 頻尿、夜間尿
- 性欲の減退
- 朝起きるのがつらい
- 慢性的な疲労感
- 甘くて温かいものを欲する
腎陽が不足すると、全身を温める力が低下します。また、腎と脾は互いに支え合う関係にあり、腎陽虚が進むと脾の機能も低下します(脾腎陽虚)。すると、身体は温まるためのエネルギー源として甘味を求めます。
6. 湿熱(しつねつ)の蓄積
これは逆のパターンで、甘いものの摂り過ぎが原因で、さらに甘いものが欲しくなるという悪循環です。
症状の特徴:
- 口の中が粘る、甘ったるい
- 身体が重だるい
- 吹き出物やニキビ
- 軟便で粘りがある、残便感
- 舌苔が厚く黄色っぽい
甘いもの、特に精製糖や脂っこいものを摂り過ぎると、体内に「湿」という病理産物が生まれます。これは余分な水分や代謝産物が滞った状態です。湿が長期化すると熱を帯びて「湿熱」となります。
湿熱があると脾胃の機能が低下し、適切に栄養を吸収できなくなります。すると身体はエネルギー不足を感じて、また甘いものを欲する――この悪循環が「砂糖中毒」とも呼ばれる状態を作り出します。
東洋医学的対策
基本原則:「脾胃を立て直す」
すべての対策の基本は、脾胃の機能を正常化することです。脾胃が健康であれば、適切に食べ物からエネルギーを得ることができ、過度に甘味を求めることもなくなります。
1. 食事療法
良質な甘味を選ぶ
すべての甘味が悪いわけではありません。東洋医学では、穏やかに脾を補う「甘味」を推奨しています:
- 穀物:米、もち米、粟、ハトムギ
- 芋類:山芋、さつまいも、じゃがいも
- 豆類:大豆、ひよこ豆、インゲン豆
- 野菜:かぼちゃ、にんじん、玉ねぎ、キャベツ
- 果物:なつめ、干し柿、りんご(加熱したもの)
- その他:はちみつ(非加熱)、甘酒、甘栗
これらは自然の甘味を含み、脾を傷めずにエネルギーを補給できます。白砂糖のように急激に血糖値を上げることもなく、満足感も持続します。
避けるべき甘味
- 白砂糖を大量に含むお菓子
- 清涼飲料水
- 人工甘味料
- 冷たいアイスクリームやかき氷
これらは脾胃を傷め、湿熱を生み出し、悪循環を作ります。
食事のリズムを整える
- 毎日同じ時間に食事を摂る
- 朝食を抜かない(特に脾気虚の人)
- よく噛んで食べる(脾の負担を減らす)
- 腹八分目を心がける
- 夜遅い食事を避ける
温かいものを摂る
- 冷たい飲み物や生ものを控える
- 温かいスープや汁物を取り入れる
- 常温以上のものを摂る習慣をつける
2. 体質別の食養生
脾気虚タイプ
- 補気食材:米、山芋、じゃがいも、かぼちゃ、にんじん、鶏肉、牛肉、なつめ
- 避けるもの:生もの、冷たいもの、脂っこいもの、食べ過ぎ
- おすすめ:山芋のとろろご飯、かぼちゃのスープ、鶏肉と野菜の煮物
脾陽虚タイプ
- 温補食材:もち米、羊肉、生姜、シナモン、黒砂糖、くるみ
- 避けるもの:生もの、冷たいもの、梨やスイカなど身体を冷やす果物
- おすすめ:生姜紅茶、羊肉のスープ、温かい甘酒
肝鬱気滞タイプ
- 疏肝理気食材:柑橘類の皮、セロリ、春菊、三つ葉、ジャスミン茶、ミント
- 避けるもの:脂っこいもの、辛すぎるもの、アルコール
- おすすめ:柑橘類の皮を使った料理、セロリのサラダ、ジャスミン茶
心脾両虚タイプ
- 補血安神食材:なつめ、龍眼肉、百合根、蓮の実、黒ゴマ
- 避けるもの:刺激物、カフェイン(夕方以降)
- おすすめ:なつめと龍眼肉のお茶、百合根の煮物、黒ゴマペースト
腎陽虚タイプ
- 補腎壮陽食材:くるみ、黒豆、黒ゴマ、海老、にら、山芋
- 避けるもの:冷たいもの、生もの
- おすすめ:黒豆茶、くるみと黒ゴマのスープ、にら玉
湿熱タイプ
- 清熱利湿食材:はと麦、小豆、冬瓜、きゅうり、緑豆
- 避けるもの:甘いもの、脂っこいもの、アルコール、乳製品
- おすすめ:はと麦茶、小豆のスープ(砂糖なし)、冬瓜と鶏肉の薄味スープ
3. 生活習慣の改善
適度な運動
- 軽いウォーキングや気功、太極拳
- 特に食後の軽い散歩は脾胃の働きを助ける
- 激しすぎる運動は気を消耗するので避ける
ストレス管理
- 深呼吸や瞑想の習慣
- 趣味や創造的活動で気を巡らせる
- 感情を適切に表現する(溜め込まない)
十分な睡眠
- 22時〜23時には就寝(胆・肝の時間を大切に)
- 7〜8時間の睡眠を確保
- 昼寝は15〜30分程度(長すぎると脾を傷める)
考え過ぎない工夫
- デジタルデトックスの時間を作る
- マルチタスクを避ける
- 自然の中で過ごす時間を持つ
4. ツボ療法
自分でできる簡単なツボ押しも効果的です。
足三里(あしさんり)
- 位置:膝のお皿の下、外側のくぼみから指4本分下
- 効果:脾胃を強化し、気を補う
- 方法:親指で円を描くように3〜5分押す
三陰交(さんいんこう)
- 位置:内くるぶしの一番高いところから指4本分上
- 効果:脾・肝・腎の三つの経絡が交わる重要なツボ
- 方法:優しく押しながら円を描く
太衝(たいしょう)
- 位置:足の親指と人差し指の骨の間、指で辿って止まるところ
- 効果:肝の気を巡らせ、ストレスを緩和
- 方法:痛気持ちいい程度に押す
中脘(ちゅうかん)
- 位置:おへそとみぞおちの中間
- 効果:胃の働きを整え、消化を助ける
- 方法:温めながら時計回りにマッサージ
5. 薬膳茶とハーブ
なつめ茶
- 大棗(なつめ)3〜5個を割って、お湯で煎じる
- 脾を補い、気血を養う
生姜紅茶
- 紅茶に生姜のすりおろしと黒砂糖を加える
- 身体を温め、脾胃を助ける
ハトムギ茶
- 湿を取り除き、脾の働きを助ける
- むくみやすい人に特におすすめ
陳皮(ちんぴ)茶
- みかんの皮を乾燥させたもの
- 気を巡らせ、消化を促進
甘味欲求との上手な付き合い方
「完全に断つ」より「質を変える」
東洋医学の智慧は、極端を避け、バランスを重視します。甘いものを完全に断つ必要はありません。むしろ、質の良い自然な甘味を適量摂ることで、身体は満足し、過度な欲求は自然と収まっていきます。
「欲求」を「身体のサイン」として読み解く
甘いものが食べたくなったら、まず自分の身体に問いかけてみましょう:
- 最近疲れていないか?
- ストレスを感じていないか?
- 食事が不規則になっていないか?
- 睡眠不足ではないか?
欲求の背後にある身体のメッセージに気づくことが、根本的な解決への第一歩です。
段階的なアプローチ
- 第一段階:白砂糖を黒砂糖やはちみつに変える
- 第二段階:お菓子をドライフルーツや甘栗に変える
- 第三段階:自然な甘味(芋や果物)で満足できるようになる
- 理想の状態:普通の食事で十分満足し、甘味への執着がなくなる
まとめ:根本から整える
東洋医学の視点から見ると、甘いものへの欲求は単なる「意志の弱さ」ではなく、身体からの重要なメッセージです。その多くは、脾胃の機能低下、ストレスによる気の滞り、慢性的なエネルギー不足が原因です。
対症療法として甘味を我慢するのではなく、根本原因である体質や生活習慣を整えることで、自然と甘味への過度な欲求は収まっていきます。そのためには:
- 脾胃の機能を立て直す
- 質の良い自然な甘味を選ぶ
- 規則正しい食事と生活リズム
- 適度な運動とストレス管理
- 自分の体質に合った食養生
これらを実践することで、甘味と上手に付き合いながら、心身ともに健康な状態を保つことができるでしょう。
東洋医学の智慧は、数千年の経験の蓄積です。現代の私たちも、この智慧を日常生活に取り入れることで、より健やかで調和のとれた生活を送ることができるはずです。
自分の身体の声に耳を傾け、自然のリズムに沿った生活を心がける――それが、甘味欲求からの根本的な解放への道なのです。